【徹底比較】医療費後払いサービス5選|気になる手数料や使い方も解説

日々の外来診療で、会計業務の効率化や未収金対策にお悩みのクリニック様は多いのではないでしょうか。
- 外来の混雑を緩和したい・・・
- 人手が足りず事務に負担がかかっている・・・
- 未収金対策をしたい・・・
そんな医療機関にとって、解決策になりうるのが本記事で紹介する「医療費後払いサービス」です。医療費後払いサービスの基本的な内容に始まり、おすすめのサービス会社や、選び方のポイントなど幅広く紹介します。医療費後払いサービスに興味を持たれている方は、ぜひ本記事を参考に導入を検討してみてください。
- 医療費後払いサービスの基礎知識(メリット・デメリット)
- おすすめの医療費後払いサービス
- 医療費後払いサービスを選ぶ際のポイント
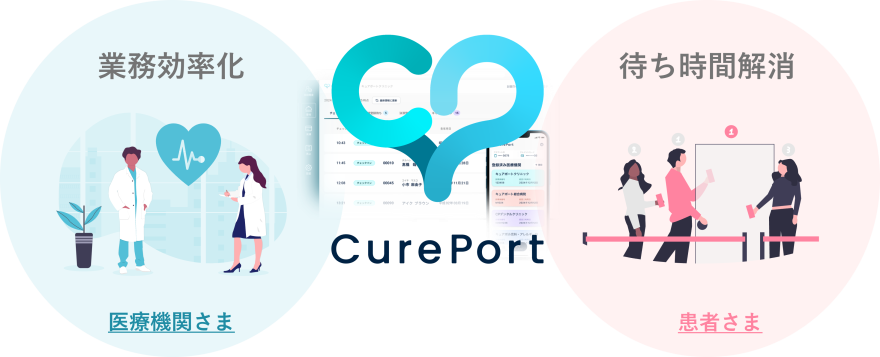
株式会社デジタルガレージは株式会社りそなホールディングスとの共同運営により、オンライン決済サービス「CurePort」をリリースしました。簡単・スピーディー・セキュアな支払い方法で、診療後の待ち時間を大幅短縮。受付機や精算機の設置が不要のため、ITに詳しい専門担当者がいなくても手軽に導入できます。
目次
医療費後払いサービスとは??
医療費後払いサービスは、患者さんが診察後に会計窓口に並ばず、後日クレジット決済や口座振替、コンビニ支払い等でまとめて医療費を支払えるサービスです。
患者さんにとっては、会計の待ち時間がなくなり、体調がすぐれない時でもすぐに帰宅できます。また、手持ちの現金を気にする必要がなくなるため、安心して受診できるようになります。
医療機関にとっては、会計業務の負担が軽減され、スタッフが他の業務に集中できるようになります。また、未収金リスクの低減にも繋がり、患者さんの利便性が向上することで、他院との差別化にもなります。
医療費後払いサービスの種類(外来・入院・在宅)
一言に医療費後払いサービスといっても、いくつか種類があります。3つの利用シーンごとにどのようなことができるのかを見てみましょう。
- 外来向け
- 入院・高額医療向け
- 在宅向け
外来向け
診察後の会計待ち時間をなくすためのサービスです。事前に登録しておけば、診察が終わった後すぐに帰宅でき、後日まとめて支払います。院内の混雑緩和や感染症対策にも役立ちます。
入院・高額医療向け
急な入院や手術などで高額な医療費が必要になった際に、後払いまたは分割払いを可能にするサービスです。退院時の精算手続きを簡略化し、患者さんの経済的負担を軽減します。
在宅向け
医師や訪問看護師が訪問した際に現金で会計を行う手間をなくすことができます。患者さんは後日まとめて支払うことで、金銭管理の負担が軽減されます。医療機関側は、訪問先での会計業務や未収金管理が不要になります。
医療費後払いサービスがおすすめの医療機関
クリニックを例に医療費後払いサービスがおすすめの医療機関を紹介します。次のような課題をお持ちのクリニックでは、医療費後払いサービスが課題解決のきっかけになるかもしれません。
- 診療後に会計待ちの列ができやすいクリニック
- 感染症対策を強化したいクリニック
- 事務スタッフの業務負担を減らしたいクリニック
診療後に会計待ちの列ができやすいクリニック
多くの患者さんが来院し、特に夕方や土曜日に会計窓口が混雑するクリニックでは、患者さんの待ち時間解消に大きく貢献します。待ち時間が減ることで、患者さんの満足度が向上し、リピーターの増加にもつながります。
感染症対策を強化したいクリニック
会計のために窓口で患者さんとスタッフが対面する時間を減らすことで、院内感染のリスクを低減できます。特に発熱外来を設けているクリニックや、待合室での感染対策に力を入れているクリニックにおすすめです。
事務スタッフの業務負担を減らしたいクリニック
毎日の会計業務(現金の受け渡し、レジ締め、未収金の管理など)を効率化できます。スタッフが他の業務(受付、患者対応、電話応対など)に集中できるようになり、業務全体の生産性向上につながります。
おすすめ医療費後払いサービス5選
医療費後払いサービス各社の特徴を見てみましょう。
病院・クリニック向けオンライン決済サービス「CurePort」|株式会社デジタルガレージ

株式会社デジタルガレージが提供する「CurePort」は、病院・クリニック向けのオンライン決済サービスです。患者はアプリで受付から会計までをキャッシュレスで行うことができ、診察後は会計を待たずに帰宅できます。医療機関は受付機や精算機が不要で、業務負担や未収金リスクを軽減できます。これにより、患者の利便性向上と医療機関の業務効率化を実現します。
CurePortの比較ポイント
- 通院時のお支払いをクレジットカードで決済可能
- 決済履歴が蓄積され、いつでも閲覧可能
- 受付機や精算機の設置が不要のため導入しやすい
製品情報
| 導入費用 | 要問合せ |
|---|---|
| 月額費用 | 要問合せ |
| 患者支払方法 | クレジットカード |
| 他サービスとの連携 | 電子カルテ・レセコン連携 |
LINE医療費後払い決済サービス「ハヤペイ」|GMOヘルステック株式会社

医療費あと払いサービス「ハヤペイ」は、クリニックに特化したLINE連携の決済サービスです。患者は事前にLINEでクレジットカードを登録するだけで、診察後、会計を待つことなくそのまま帰宅できます。
支払いは後日自動で行われ、領収書や診療明細書もLINEで受け取れるため、院内での待ち時間を大幅に解消し、利便性を向上させます。また、医療機関側も未収金リスクの低減と自動での入金消込が可能になります。
ハヤペイの比較ポイント
- 会計待ちなし、診察後すぐ帰宅できる
- LINE完結で支払いや領収書受取が楽
- 未収金リスクを軽減し事務作業を効率化
製品情報
| 導入費用 | 要問合せ |
|---|---|
| 月額費用 | 要問合せ |
| 患者支払方法 | クレジットカード |
| 他サービスとの連携 | 電子カルテ・レセコン連携、LINE連携 |
医療費あと払い|株式会社メディカルファイナンステクノロジーズ

「医療費あと払い」は、医療機関のニーズに合わせたさまざまな後払いサービスを提供しています。
- 外来向け
- オンライン・電話診療向け
- 在宅向け
- 薬局向け
この4種類のなかから、自院に適したサービスを選べるのです。しかも、WEB上で完結するサービスなので、低コストで導入できます。期限を過ぎても医療費の支払いがない場合は、督促業務を代行してくれるので医療機関側の負担軽減にもつながるでしょう。
医療費あと払いの比較ポイント
- ニーズに合わせた4つのサービスがある
- 低コストで導入できる
- 督促業務を代行してもらえる
製品情報
| 導入費用 | 要問合せ |
|---|---|
| 月額費用 | 要問合せ |
| 患者支払方法 | 口座引落・ドコモ利用料とまとめて支払・ソフトバンク利用料とまとめて支払・au利用料とまとめて支払・EPARK後払い(クレジットカード) |
| 他サービスとの連携 | なし |
CADA2|CADA株式会社

「CADA2」は、入院費・高額医療費の支払いをサービス提供会社が立て替えてくれます。医療費立て替えによって、未収金の防止・抑制につながるので病院にとってはありがたいサービスです。
導入の申し込みから利用開始までは、約3週間~4週間で比較的スムーズに導入できます。患者も申し込みから2~3日で審査が完了して利用できるようになり、急ぎの場合は即時での審査も可能です。
CADA2の比較ポイント
- 立替払いをしてもらえるので未収金のリスクを抑えられる
- 導入にかかる期間が短い
- 患者の利用審査は急ぎの場合即時対応している
製品情報
| 導入費用 | なし |
|---|---|
| 月額費用 | 要問合せ |
| 患者支払方法 | 要問合せ |
| 他サービスとの連携 | なし |
歯科医院様向けの医療費後払いサービス
歯科医院様向けの医療費後払いサービスも紹介します。
【歯科医院様向け】会計あと払い post-pay|株式会社ミック

歯科医院様向けの「会計あと払い post-pay」は、患者さんの会計待ち時間をゼロにし、利便性を高めるサービスです。
クレジットカードによる後払いで、未収金リスクと会計業務の負荷を軽減します。未成年のお子様の通院や訪問診療など、その場での現金支払いが不要になり、患者満足度向上と業務平準化に貢献するキャッシュレス決済サービスです。
医療費後払いサービスの導入メリット
医療費後払いサービスの導入メリットを紹介します。ここでも、クリニックの外来を例に、クリニック側、患者さん側それぞれの導入メリットを見てみましょう。
| クリニック側 | 患者さん側 |
|---|---|
|
|
|
クリニック側の導入メリット
クリニック側には次のような効果が期待できます。
- 業務効率の向上
- 未収金リスクの低減
- 患者満足度の向上
- 感染症対策
業務効率の向上
診察、治療後の会計、スタッフが現金の受け渡しやレジ締めに費やす時間が削減されます。
未収金リスクの低減
医療費後払いのサービス会社が患者さんから代金を回収するため、クリニック側の未収金リスクが大幅に軽減されます。
患者満足度の向上
会計待ち時間がなくなることで、患者さんのストレスが減り、クリニックの評価向上やリピート率につながります。
感染症対策
窓口での滞在時間が短縮され、対面接触を減らせるため、院内感染のリスクを下げることができます。
患者さん側の導入メリット
患者さんには次のような導入メリットがあります。
待ち時間の解消
診察後すぐに帰宅でき、会計のために待つ必要がなくなります。
利便性の向上
体調が悪い時でも、現金やクレジットカードの準備を気にせず受診できます。
安心感
高額な医療費でも、後日まとめて支払うことができるため、安心して治療を受けられます。
医療費後払いサービスのデメリット
続いて、医療費後払いサービスを導入した際に想定されるデメリットについても見てみましょう。こちらも同じくクリニックの外来を例に、クリニック側、患者さん側それぞれについて紹介します。
| クリニック側 | 患者さん側 |
|---|---|
|
|
|
クリニック側のデメリット
まずはクリニック側のデメリットです。サービス利用料がかかることや、院内で利用環境を整えること、患者さんへの周知などが課題となります。
コストの発生
導入費用や月額固定費用、決済手数料など、サービス利用にかかるコストが発生します。
導入の手間
サービスの導入にあたり、システム設定やスタッフへの周知が必要になります。
利用者層の限定
デジタルに不慣れな高齢者など、一部の患者さんは利用をためらう可能性があります。
患者さん側のデメリット
続いて、患者さん側のデメリットです。
手数料の負担
サービスによっては、利用ごとに手数料が加算される場合があります。
利用のハードル
事前登録が必要な場合があり、特に高齢者にとっては手続きが煩雑に感じられることがあります。
医療費後払いサービスの使い方は?
医療費後払いサービスの一般的な利用の流れは次の通りです。ここでも、外来を例に紹介しています。
- 事前登録
- 受診
- 会計不要
- 後日支払い
STEP01 事前登録
多くのサービスでは、最初に患者さんの情報(氏名、連絡先、支払い方法など)をWebサイトやアプリで登録します。
STEP02 受診
登録済みの患者さんは、受付で「後払いを利用したい」と伝えるだけで、通常の診察に進みます。
STEP03 会計不要
診察が終わったら、会計窓口に並ばずにそのまま帰宅できます。
STEP04 後日支払い
登録した支払い方法(クレジットカード、コンビニ払い、口座振替など)で、後日サービス会社を通じて医療費が支払われます。
医療費後払いサービスの利用料金・手数料は?
医療費後払いサービスは、患者さんではなく、クリニック側が料金を負担することが多いです。医療費後払いサービスで発生する料金は次の通りです。
- 初期費用
- 月額費用(固定費)
- 決済手数料(従量課金)
初期費用
システムの導入にかかる費用で、0円から数十万円まで幅があります。近年は、初期費用を無料としているサービスも増えています。
月額費用(固定費)
毎月支払うシステム利用料です。こちらも月額無料から数千円、場合によっては1万円を超えるサービスまで様々です。利用件数が少ない月でも発生するため、導入前にシミュレーションすることが重要です。
決済手数料(従量課金)
最も主要な費用で、患者さんの支払い金額に応じて発生します。これは、患者さんが後払いを利用して支払った医療費の総額に対する一定の割合(パーセンテージ)で計算されることが多いです。一般的な相場は、決済金額の1%台後半から5%程度ですが、サービスの種類(クレジットカード、コンビニ払いなど)やプランによって異なります。
医療費後払いサービスを選ぶ際のポイント
医療費後払いサービスを選ぶ際は、コスト面や患者層に合ったものを見極めることが重要です。以下のポイントを参考に比較検討することをおすすめします。
- 料金体系とコストパフォーマンス
- 利用のしやすさ
- サポート体制と信頼性
料金体系とコストパフォーマンス
導入費用やランニングコストがどのくらいかかるかを確認します。特に、自院の月間利用件数で試算し、長期的なコストパフォーマンスが良いかを見極めましょう。
利用のしやすさ
患者さんが簡単に登録できるかを確認します。スマートフォンやPCに不慣れな高齢の患者さんが多い場合は、院内に専用端末があるサービスや、家族が代理で登録できるサービスが有効です。
また、支払方法の種類も大事なポイントです。クレジットカード、コンビニ払い、口座振替など、多様な支払い方法に対応しているかを確認します。患者さんの利便性が向上し、利用率が高まります。
サポート体制と信頼性
お金に関わるサービスであるため、サービス会社の信頼性は非常に重要です。導入実績は選ぶ際の1つの指標になります。
導入時のサポートや、導入後のトラブル対応が充実しているかを確認しましょう。患者さんからの問い合わせ対応を代行してくれるサービスもあります。
まとめ
本記事では医療費後払いサービスについて、基本的な内容から、おすすめのサービス会社、選び方のポイントなど網羅的に紹介してきました。
来院される患者さんの属性によっては、医療費後払いサービスの導入が「外来の混雑緩和」「業務効率化」につながる可能性があります。
サービス会社によって利用方法や料金体系が異なるので、導入を検討されている方は本記事を参考にそれぞれ比較してみてください。








