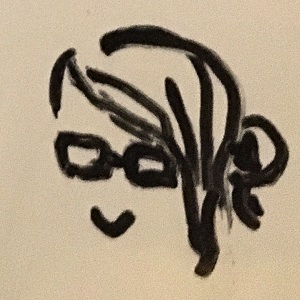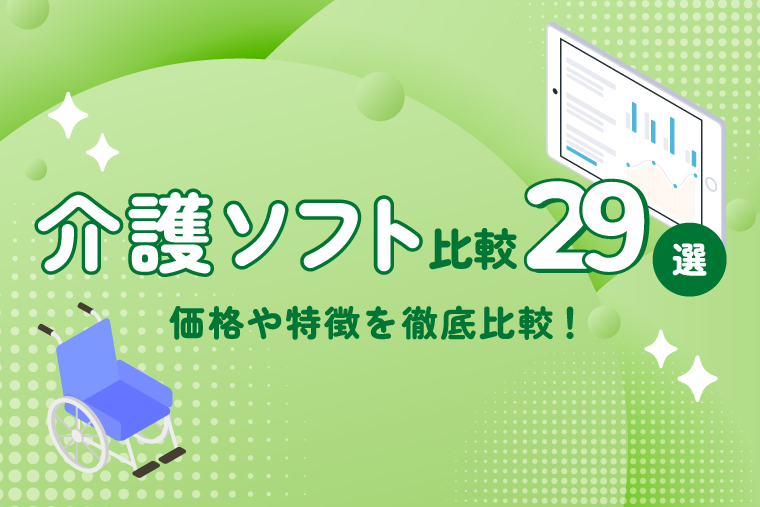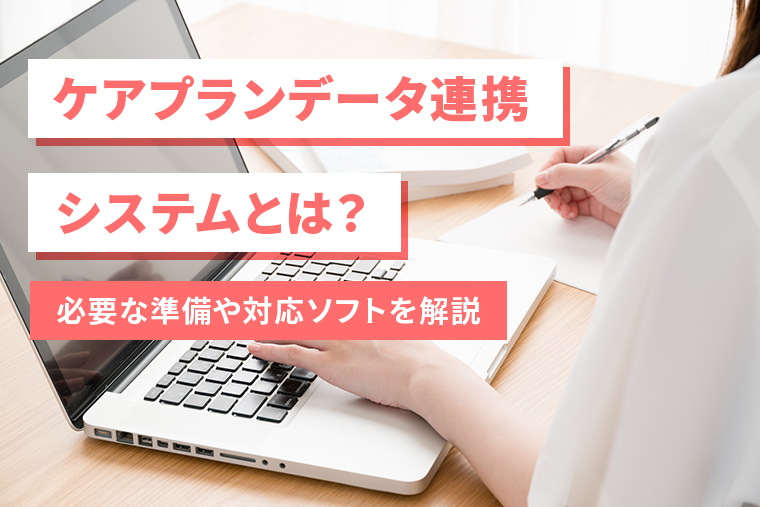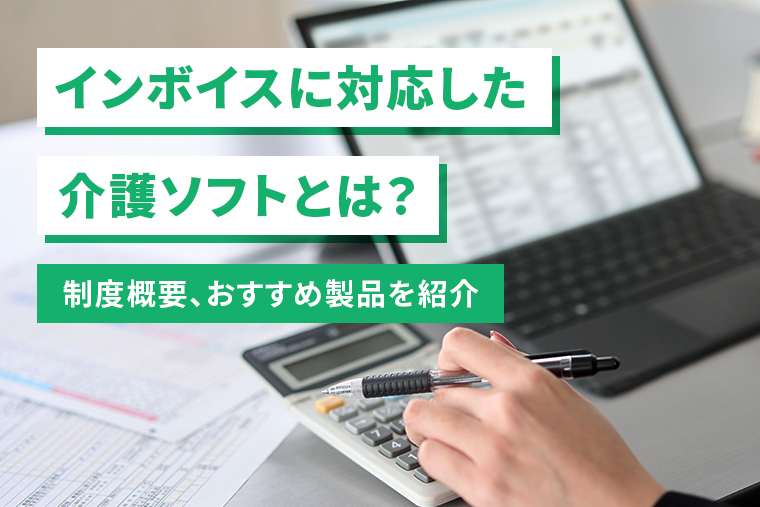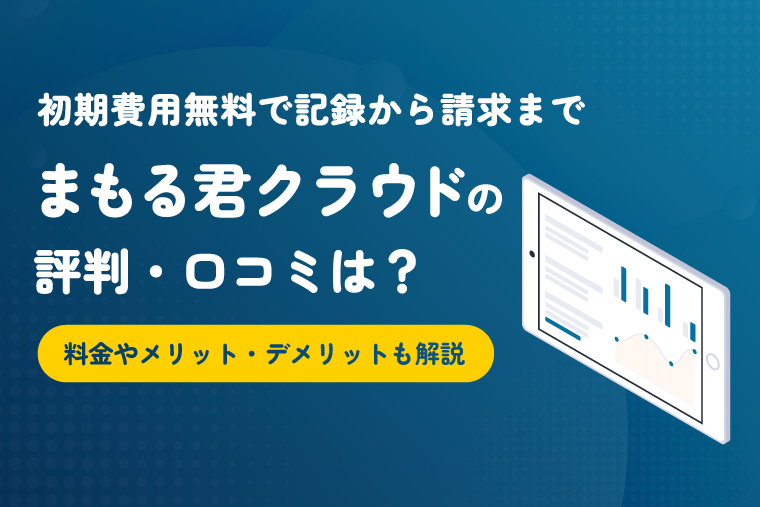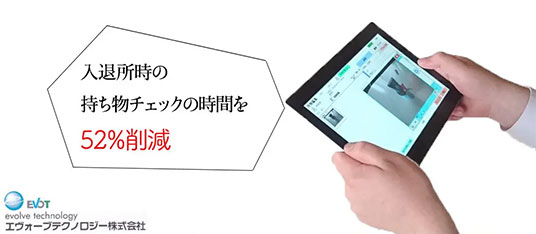介護業界の課題を解決するICT化とは?活用事例もあわせて紹介!
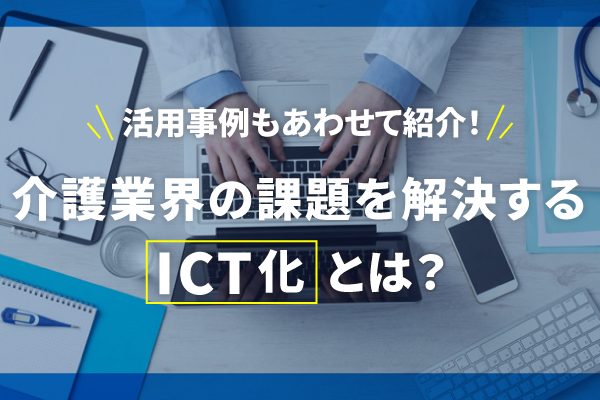
介護業界における人手不足が叫ばれる中、厚生労働省が主導となって、介護業界のICT化を推進しています。
しかし、ICT化を進める理由や進めることによるメリットについてよく知らないため、なかなか導入に踏み切れていない事業所も多いのではないでしょうか。介護分野でのICT化は、人手不足で悩む業界の働き方を見直す上で、重要になってきます。
本記事では、介護業界でICT化が推進される理由、メリットなどについて紹介します。ICTを活用した事例や導入に利用できる補助金などの情報も解説。ICT化を進めたいと考えている事業所や担当者様はぜひご覧ください。
介護業界で導入が推進されるICTとは
まず、介護業界で導入が推進されるICTについて解説します。
ICTは「Information and Communication Technology」の頭文字をとった略称です。日本語訳では情報通信技術といわれており、インターネットのような情報通信技術を利用したコミュニケーションを意味します。
身近な例としては、SNSやメール、チャットなどもICTに含まれます。介護業界におけるICTは、これまでの紙媒体による情報のやりとりを電子化し、新たなインフラとして導入していく動きが求められています。
利用者情報が記載されている介護記録や、行政に提出する文書などのデータを電子化することで、業務を効率化することが可能です。業務効率が改善することで、介護サービスの提供に集中できることも期待されています。
また、ICT化でさまざまな種類のデータを集積したビッグデータの蓄積ができるようになるでしょう。ビッグデータを分析することにより、エビデンスに基づく介護サービスの提供を促進することにもつながります。
介護業界でICT化が求められている理由
介護業界でICT化が推進されている理由には、日本の抱える課題が関わっています。その課題とは次のとおりです。
- 介護業界の慢性的な人手不足
- 日本人の4人に1人が75歳以上の後期高齢者になるとされる2025年問題
現状でさえ給与水準の低さや過酷な労働実態から、人手不足に悩まされています。また、2035年には85歳以上の人口が1000万人に到達すると推計されています。さらに介護を必要とする高齢者が増えることが予想され、介護を受けたいのに受けられない介護難民が生じるでしょう。
さらに、人手不足により一人ひとりの業務が多忙になれば、介護サービスの質の低下も懸念されます。
2025年には日本人の4人に1人が75歳以上の後期高齢者になるとされる「2025年問題」があり、人手不足の問題はますます加速していくでしょう。
将来の課題を解決し、より質の高いサービスを提供するためには、業務を効率化して、生産性の向上を促すICT化が推進されています。
介護業界におけるICT化を進める4つのメリット

介護業界がICT化を進めることによるメリットは、次の4つです。
①ICTの活用による加算取得
②より手厚い介護体制による利用者様の満足度向上
③スタッフの業務負荷の軽減
④事業所間における連携の向上
それぞれのメリットについて、詳しく解説します。
①ICTの活用による加算取得
ICTを活用することで、介護報酬の加算を取得しやすくなります。
たとえば、厚生労働省が運用している科学的な介護をおこなうためのデータベース「科学的介護情報システム(LIFE)」を活用することで加算を取得可能です。
事業所でおこなっている介護の計画や内容をLIFEに入力したり、LIFEのデータを介護に活用したりすることで、科学的介護推進体制加算が算定されます。
また、定期的に利用者様のもとに訪れる定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスについても、ICT機器の利用により導入しやすくなりました。
さらに、2018年介護報酬改定で新設された「排せつ支援加算」も、ICTを利用し、排せつの分析をしてデータを提出することで加算を取得できます。
ICTを活用することで人手を増やすことなく、加算の取得が可能です。
②より手厚い介護による患者様・利用者様の満足度向上
介護業界の業務は、直接患者様や利用者様に介護サービスを提供するだけではなく、介護記録やスタッフ間の情報共有などの記録や書類作業も含まれます。介護ソフトなどのICTを導入することで、記録や書類作業の手間が少なくなり、患者様・利用者様と関わる時間を増やせるでしょう。
一人ひとりに十分な介護サービスを提供する時間が確保できれば、質の高い介護を提供しやすくなります。その結果、より手厚い介護を提供できるようになり、患者様・利用者様の満足度向上につながるでしょう。
③スタッフの業務負荷の軽減
たとえば、ICTのひとつである介護ソフトを活用することで、介護記録やケアプラン、アセスメントチャートの作成が簡単になり、業務負荷が軽減します。
過去に記入しておいたデータをすぐに検索したり、数値を記入しておいたりすることが可能となるため、一から調べて記入する必要がありません。
また、タブレットデバイスを活用することで、職場の決まった場所でしかできなかった入力作業が、場所を選ばずに空いた時間を有効活用できます。ICTの活用により、スタッフの業務負荷が軽減され、より働きやすくなるでしょう。
④事業所間における連携の向上
ICTで情報が電子化されることにより、事業者間や医療機関との連携の質が向上します。
従来の紙媒体による情報共有では、作成に手間がかかったり、相手の手元に到着するまでに時間がかかったりして非効率でした。
ICTを導入すれば、情報共有が電子化され、事業者間や医療機関との連携が容易になります。迅速に適切な情報共有がなされることにより、情報伝達ミスや遅れなどによる課題を解消できるでしょう。
介護業界のICT化が思うように進まない3つの理由
介護業界のICT化には多くのメリットがあり、徐々にICT化が進んでいます。公益社団法人介護労働安定センターの調査によると、コロナ禍の2020年3月以降、新たにICTを導入した事業所の割合は、全体の44.8%に上りました。
今後ますます介護業界のICT化は進んでいくでしょう。ICT化をより進めるには、介護業界のICT化を妨げる次の3つの理由を解決しなければなりません。
①今までに発生していなかったコストがかかる
②年配のスタッフもおり、スタッフがしっかり使いこなせることができるか
③本当に業務負荷が軽減するのか不安
それぞれの理由について、詳しく見ていきましょう。
①今までに発生していなかったコストがかかる
ICTの導入には、利用するためのパソコンやタブレットなどのデバイス、介護システムなどの導入・維持管理コストがかかります。パソコンやタブレットのデバイスの購入費には数万円以上かかり、介護システムは月々の利用料といったランニングコストがかかるでしょう。
今まで発生していなかったコストがかかることが、ICTの導入に踏み切れない理由のひとつです。
しかし、ICT化することで業務の効率UPにつながるため、長期的に見ればプラスになる面が大きいともいえます。
また、ICTの導入には地域医療介護総合確保基金による「ICT導入支援事業」という補助金を利用することが可能です。ICT導入支援事業では、下記の補助金額を受けられます。
補助上限額
事業所規模(職員数)に応じて設定
- 1〜10人 100万円
- 11〜20人 160万円
- 21〜30人 200万円
- 31〜 260万円
補助率
都道府県が設定
※事業者負担を入れることが条件
補助対象
- 介護ソフト
- タブレット端末
- スマートフォン
- インカム
- クラウドサービス
- 他事業者からの照会経費など
- Wi-Fi機器の購入設置
- 業務効率化に資するバックオフィスソフト(勤怠管理、シフト管理など)
補助金を活用することで、コストを抑えてICTを導入することができるでしょう。
②年配のスタッフもおり、スタッフがしっかり使いこなせることができるか
ICT化はパソコンやタブレットなどのデバイスを使用したり、新たな介護ソフトを導入したりするため、新たに使用方法を習得する必要があります。そのため、年配のスタッフや従来の紙媒体に慣れている方は、ICTの導入に否定的な感情を抱いてしまうかもしれません。
また、普段からパソコンやタブレットを使い慣れていない方は、慣れるまで時間がかかるでしょう。スタッフがしっかりと使いこなすことができず、一時的に業務がやりにくくなってしまう可能性があることもICT化に踏み切れない理由となっています。
③本当に業務負荷が軽減するのか不安
ICT化は新たな取り組みであるため、本当に業務負荷が軽減するのか不安だという方もいます。使い方を覚えなければならなかったり、ICT化によって作業が増えたりして、結果的に業務負荷が軽減しないのではないかと不安を抱える方が多いのです。
ICT化を進めるためには、導入することでどのように業務負荷が軽減するのかメリットやケースを提示して、不安を解消していく必要があるでしょう。
介護業界におけるICT活用の事例
介護業界におけるICTは、介護記録や保険請求をおこなう介護ソフトだけではありません。ここでは、実際に介護業界で使用されているICTを活用した事例を紹介します。
①介護支援ソフト
介護支援ソフトは、日々の介護記録やケアプランの作成、介護保険の請求など、介護業界の業務をおこないやすくなるソフトです。
紙媒体での記録では記録に時間がかかりますし、後で見返す時に探すのも大変でしょう。介護支援ソフトを利用すれば、過去のデータを調べやすいことはもちろん、データを自動で取り込んで反映してくれるので、業務が効率化します。
介護ソフトについては【2024年版】おすすめ介護ソフト29製品を徹底比較|選び方まででも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
②見守りシステム・センサー
見守りシステム・センサーは、遠隔で患者様・利用者様の状況を確認、徘徊やベッドから離れていないかを感知したりする機器です。
患者様・利用者様のなかには、一人で自宅や施設から外出してしまったり、安静にしなければならないのにベッドから離れてしまったりする方がいます。しかし、徘徊やベッドから離れないように患者様・利用者様に付きっきりになってしまうのは、人手が必要です。また、見落としてしまうかもしれません。
見守りシステム・センサーを導入すれば、遠くにいても利用者の状況を感知できるため、他の業務をおこなったり、見落としを回避したりできます。
また、テレビ電話のように画面を通して会話できるものもあり、遠隔で体調の変化を確認することも可能です。
離床センサーについてはおすすめ離床センサーのメーカー10選|種類や価格も解説でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
③排せつ支援
排せつ支援は、排せつした時を知らせたり、排せつするタイミングを予測したりするICT機器です。排せつ後の迅速なおむつ交換や排せつするタイミングを予測することで、適切なトイレ誘導などを実現します。
感知するシステムとしては、排せつ物のにおいを感知するタイプやおむつが濡れたことを感知するタイプ、超音波で膀胱の尿量を測定するタイプなどさまざまです。排せつ支援のICT機器を利用し、排せつの分析をおこなうことで、加算取得につながります。
④地域・医療連携システム
地域・医療連携システムは、事業所や医療機関、施設との連携を強化するシステムです。患者様・利用者様によっては転院するケースや、複数の事業所が介入するケースなどがあります。
質の高い介護を提供するためには、迅速で充実した情報共有が欠かせません。地域・医療連携システムを利用することで、患者様・利用者様の情報を関係者で共有できます。
その結果、業務の効率化や良質な介護サービスの提供につながります。
ICT化を進めて働きやすい職場で質の高い介護を提供しましょう

介護業界の人手不足や高齢化社会による介護需要の増加は、今後ますます高まっていくでしょう。しかし、すぐに介護人材を増やすことは難しいのが現状です。
そのため、ICT化を進めて、作業効率の改善や働きやすい職場環境に変えていくことが、介護業界の課題を解決する鍵になるでしょう。また、データを活用することで、より質の高い介護サービス提供にもつながります。
ICT化を進めて、介護業界の課題を解決し、よりよい介護サービスを提供しましょう。