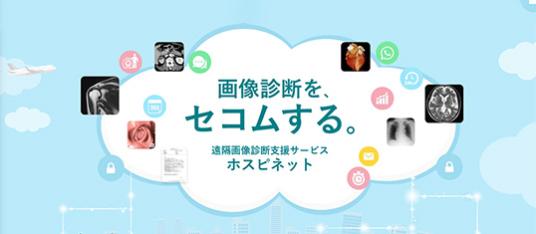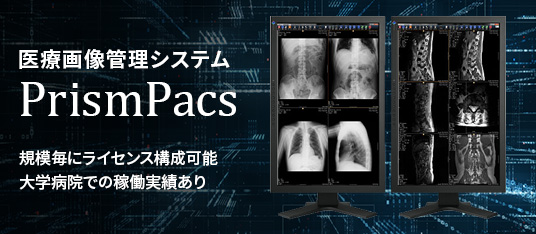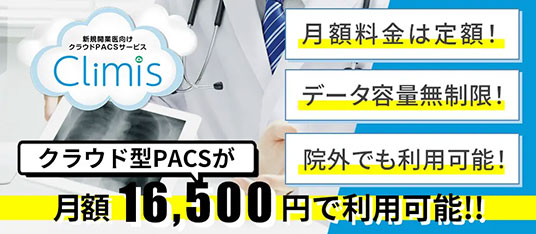【2026】PACSメーカーを徹底比較|選び方や導入メリットまで

医療の高度化や撮像装置の性能向上により、画像検査の件数や検査時の画像枚数が増加しています。物理的なフィルムを用いていると、保管スペースや運搬・管理等の手間が膨大なものとなってしまうでしょう。
そのような点を解決してくれるのが、電子化した検査画像を管理する「PACS」で、近年普及が進んでいるのです。当記事ではPACSの選び方やそれぞれのメーカーの特徴を、詳しく解説していきます。PACSの導入を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
- PACSの種類・施設規模別のおすすめメーカー
- PACSを選ぶ時のポイント
- PACSの導入メリット
最初に3社のPACSをご紹介します。運用形態(オンプレミスorクラウド)、対象施設規模、料金形態などに注目してそれぞれのPACSを比較してみましょう。
 |
 |
 |
|
| 製品名 | PrismPacs | ClimisクラウドPACSサービス | LOOKREC(ルックレック) |
| 企業名 | 株式会社プリズム・メディカル | 株式会社ジェイマックシステム | 株式会社エムネス |
| 運用形態 | クラウド/オンプレミス | クラウド | クラウド |
| 料金携帯 | 施設規模に応じてお見積り | 月額16,500円~ | 要問い合わせ |
| 対象施設規模 | クリニック~大学病院 | クリニック ※病院向け製品もあり | クリニック、大学病院、健診センター |
| 特長 | PACSをはじめ健診システム、線量システムなど幅広い製品ラインナップ | 新規開業医が低コストで導入可能な料金設計 | 画像の保管だけでなく遠隔読影の依頼等もスムーズに依頼可能 |
| お問い合わせ |
お問い合わせ
|
お問い合わせ
|
お問い合わせ
|
- 業界に精通したコンシェルジュが希望に合うサービス・業者を厳選してご案内します
- ご利用は完全無料!
PACSとは?
PACSは、医療機関で撮影されたX線、CT、MRIなどの画像をデジタルデータとして保管・管理するためのシステムです。従来のフィルム運用と比べて、画像の検索・比較が容易になります。診断や治療の効率化、情報共有の円滑化、保管スペースの削減など、多くのメリットがあります。
PACSメーカーを一挙に紹介!
ここから、PACSメーカー各社の製品を見ていきましょう。
PrismPacs|株式会社プリズム・メディカル

PrismPacsは大学病院での稼働実績を持つPACSです。整形計測機能など、専科の機能を標準搭載しています。医療施設の規模に応じたライセンスモデルを採用しているため、診療所から大規模総合病院まで、幅広い医療施設に対応可能です。個々のユーザー、施設で最も使い勝手のいい設定ができます。
画像を用紙やフィルムへ実寸印刷ができること、動画サーバーなしでも動画をスムーズに表示できること等、お客様にとって使いやすい機能にこだわっています。
PACSだけではなく、健診システムや線量管理ソフトなど自社で幅広い製品ラインナップを開発・販売している点もプリズム・メディカルの特徴です。
>>>プリズム・メディカルの健診システムはこちらのページで紹介しています。
PrismPacsの比較ポイント
- 大学病院での稼働実績
- 整形計測機能など、専科の機能を標準搭載しています
- 個々のユーザー、施設で最も使い勝手のいい設定が可能
製品情報
| 種別 | オンプレミス/クラウド |
|---|---|
| 特長 | 施設規模に応じた柔軟な料金設定 |
| 導入対象施設 | クリニック~大学病院 |
| セキュリティ | 要問合せ |
| サポート・保守体制 | 要問い合わせ |
ClimisクラウドPACSサービス|株式会社ジェイマックシステム

ジェイマックシステムは、メディカルスタッフを中心に、未来の理想的な医療システムを目指して創られた会社です。医療現場で患者さんと向き合い、経験を積んだスタッフや最先端のITスキルを持つスタッフが製品を作っています。
クリニックの開業時に様々な費用がかさみ、PACSの導入にはなかなか踏み込めないこともあるかと思います。そのような声にお応えしてできたのが、「Climis クラウドPACSサービス」です。低価格に抑えた初期費用と月額料金にて利用が可能となっています。
Climis クラウドPACSサービスの比較ポイント
- 低コストにて導入が可能
- 月額費用の変動なくデータ容量が無制限!
- タブレット対応で外出先からも利用可能
製品情報
| 種別 | クラウド型 |
|---|---|
| 特長 | タブレット対応により往診や院外利用も可能 |
| 導入対象施設 | クリニック |
| セキュリティ | 要問合せ |
| サポート・保守体制 | トータルサポートサービスの契約で迅速な対処が可能 |
XTREK series|株式会社ジェイマックシステム
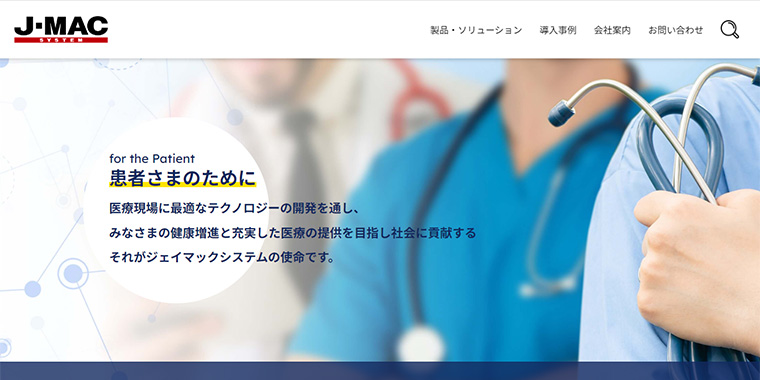
ジェイマックシステムはクリニック向けだけでなく、病院向けにもPACSを開発しています。PACS専業メーカーとして培ったノウハウで、医療機関での様々なニーズに柔軟に対応可能です。
診断現場の声から生まれた多彩な機能を搭載しており、日常の読影業務から、カンファレンスや資料作成までサポートします。
XTREK seriesの比較ポイント
- マトリクス形式の表示で見やすい
- 内臓脂肪計測機能を標準搭載
- 日本語表記ボタンで簡単操作が可能
製品情報
| 種別 | オンプレミス型/クラウド型 |
|---|---|
| 特長 | 電子カルテやフィルムレス運用、災害対策や地域医療連携などに柔軟に対応可能 |
| 導入対象施設 | 大規模病院~クリニック |
| セキュリティ | 要問合せ |
| サポート・保守体制 | トータルサポートサービスの契約で迅速な対処が可能 |
クラウドPACS「LOOKREC(ルックレック)」|株式会社エムネス

放射線診断専門医が創業し、放射線診断専門医が約10名常勤している遠隔画像診断のパイオニアであるエムネス。
そんなエムネスが提供するクラウドPACS「LOOKREC(ルックレック)」は、現役医師とIT専門家がタッグを組み開発。医師目線で開発されたからこそ使いやすさに定評があり、全国で1,170施設以上(※2024年9月時点)に導入されています。
低コストかつ安全に安全基準に準拠したGoogle Cloud Platformを利用し、より自由にDICOMデータの共有が可能になります。
クラウドPACS「LOOKREC(ルックレック)」の比較ポイント
- 世界トップレベルのセキュリティ対策がされたGoogleクラウドを利用
- 導入費・更新費、基本0円
- 現役放射線科医が開発したので使いやすい
製品情報
| 種別 | クラウド型 |
|---|---|
| 特長 | 専用設備不要!遠隔読影の依頼・レポート受診、予防×治療の連携、病病連携も可 |
| 導入対象施設 | クリニック、健診センター、病院 |
| セキュリティ | ・SSAE16/ISAE3402TypeⅡ(SOC1/SOC2/SOC3),ISO27001 , ISO27017 , ISO27018の各監査に対応済みのGoogleCloudPlatformを採用 ・HIPPA準拠 ・ISMSクラウドセキュリティ認証の取得 ・2段階認証機能、アクセス権限設定、ログイン後の追跡管理可能 |
| サポート・保守体制 | ・導入や操作方法のご説明・サポート有(※訪問が伴う対応の場合、別途費用発生の可能性有) ・アフターサポートとしてカスタマーサポート在籍 |
FINO.VITA.GX|コニカミノルタジャパン

コニカミノルタの『FINO.VITA.GX』は、FINO.Worklist・FINO.View.Pro・FINO.Drive・FINO.Report(オプション)から構成しており、各機能に特化したアプリケーションを利⽤することが可能です。永年培ってきた技術を集約し、医療現場の画像診断・管理業務を強⼒にサポートします。
C@RNACORE|富士フイルムメディカル
富士フイルムならではの高度な画像処理と使いやすさが特徴のPACSが「C@RNACORE」です。診たい部分を的確に描写する画像処理機能が装備されています。シンプルで使いやすく、電子カルテとも連携できる、クリニック向けのワークステーションです。
画像以外の検体検査データも、ひとつの画面に表示できるので、一目で状況を把握できます。また、骨塩測定機能も付いており、骨粗しょう症のスクリーニング検査にも最適です。
WATARU|株式会社スリーゼット

株式会社スリーゼットは「ニーズから、発想する。」をスローガンに、自社開発にこだわった会社です。医療現場のIT化発展に尽力し、今では2000施設でスリーゼットのシステムが導入されています。
WATARUはクリニック向けに特化し、開発されたPACSです。コンパクトなボディに高性能のシステムが凝縮されています。電子カルテとの連携はもちろんのこと、マンモビューアなど複数モダリティとの連携が可能です。診察効率を大幅にアップさせる効果が期待できるでしょう。
クラウド PACS NOBORI|PSP株式会社

もともとは株式会社NOBORIとして、サービスを展開していたクラウドPACS「NOBORI」ですが、2022年4月にPSP株式会社と合併し「PSP株式会社」となりました。最新鋭のセキュリティシステムで、データを安全に保管してくれます。
NOBORI-CUBEという専用のアプライアンスをレンタルするだけで、初期投資ゼロで導入が可能です。数年ごとのサーバーの買い替えも不要なので、比較的コストを抑えることができるでしょう。
RapideyeCore|キヤノンメディカルシステムズ株式会社

RapideyeCoreは医療現場で流通するさまざまな形式のデータを統合管理可能なアーカイブシステムを採用しています。DICOMデータはもちろん、動画データ・汎用ファイルなど1つのサーバに保管し管理、利用が可能です。連携病院であれば検査をどの施設からでも、画像参照、更にはレポート作成が可能。他施設へ勤務されている先生に相談したい場合、どの施設でも読影が可能なため、働き方改革にも寄与します。
Claio|株式会社ファインデックス

株式会社ファインデックスは、全国の医療機関の診療を支援するソリューションを提供している会社です。画像ファイリングシステムClaioは、院内のさまざまなデータを統合管理するためのシステムとして開発されました。
多くの国公立大学病院で導入されていますが、Claioを総合的に導入するためには、医療システムに関する高い知識が求められます。一般の診療所や小規模病院では、Claioをベースとしながらも、比較的簡易な操作性のClaio Boxがおすすめです。
Xronos|ライフサイエンスコンピューティング株式会社

ライフサイエンスコンピューティング株式会社はITを通じて、地域医療の拡充を目指すメーカーです。Xronosはライフサイエンスコンピューティングが自社開発した医療画像管理システムで、iPhoneやiPadなどのモバイルにも対応しています。
ソフトウェアのみの提供が可能で、参照用Webビューワは無償提供されるため、初期費用を抑えた導入が可能です。オプションで遠隔読影サービスやクラウドサービスといった機能を付けることもできます。施設の環境や使い方に合わせて、最適のシステムを用意できるでしょう。
PACSの価格相場は?
では、PACSの利用料金はどれぐらいになるのでしょうか。ここではオンプレミス型のPACSを例に料金イメージを見てみましょう。下記、PACSメーカー様にヒアリングをした内容をもとに表を作成しています。メーカーによって価格帯が異なりますので、参考程度にみて貰えればと思います。
| クリニック初期費用 |
|
|---|---|
| 中小規模病院初期費用 |
|
| 保守料金 |
|
※こちらの金額には、既存PACSからのデータ移行費用や、各種モダリティとの接続費用などの費用は含まれていません。
PACSを選ぶときに見るべきポイント
PACSを導入する際に、どのように選べば良いのか迷う方も少なくありません。PACSを選ぶ際には、下記の4点を中心に選んでいきましょう。
- クラウド型かオンプレミス型か
- セキュリティの安全性は?
- 保守やサポート体制は?
- 価格は?
ここからは、選ぶポイントを具体的に掘り下げていきます。
①クラウド型かオンプレミス型か
電子カルテと同じように、PACSにもクラウド型とオンプレミス型があります。クラウド型が画像をクラウド上に保存するのに対し、オンプレミス型は院内のサーバーに画像を保存するのが大きな違いです。
近年の傾向としては、クラウド型がトレンドとなっています。クラウド型・オンプレミス型のメリットとデメリットをそれぞれ知ったうえで、どちらのタイプにするかを選ぶようにしましょう。
以下では、クラウド型・オンプレミス型それぞれのメリットとデメリットを解説していきます。
クラウド型のメリット・デメリット
クラウド型のメリットは、外部のデータセンターにデータを保管するため、他施設のデータを共有しやすいという点です。さらに自前で保守管理する手間がないので、今後データが膨大になったときも安心できるでしょう。
クラウド型であれば、申し込み後に簡単な設定をするだけで使用可能になります。導入が比較的楽なのも、クラウド型のメリットといえるでしょう。
デメリットとしては、システム利用料がかかるという点が挙げられます。クラウド事業者のサーバーを利用するため、月額または年額でシステム利用料を支払わなければなりません。データ容量に応じて月額料金が高くなることがあるので、将来的にいくらぐらいのランニングコストが発生するのかをよく計算しておきましょう。
オンプレミス型のメリット・デメリット
オンプレミス型PACSのメリットは、システムとデータをすべて自分たちで管理できる点です。これにより、ネットワーク接続に依存しないため、通信速度の影響を受けずに安定した運用が可能です。さらに、組織の要件に合わせてカスタマイズしやすいという利点もあります。
一方で、初期費用が高額になりやすいのがデメリットです。サーバー機器やソフトウェアの購入・システム構築などのお金がかかります。オンプレミス型は、多少高額でもセキュリティ面をしっかりさせたい方や、社内システムとの連携を図りたい方におすすめです。
②セキュリティの安全性は?
システム動作の安全性や画像データ保存の安全性・真正性は特に重要になってきます。たとえば株式会社NOBORIの「クラウドPACSNOBORI」は、データの多重管理や、暗号化を用いた堅牢なセキュリティを構築しています。
システムの技術的な対策はもちろん、サイバー攻撃によるセキュリティインシデント対応体制の整備を整えている企業のPACSを選ぶようにしましょう。
③保守やサポート体制は?
保守やサポート体制も、PACSを導入する上で重要になってきます。医用画像は大切なデータです。システムの稼働率はもちろん、万が一不具合が生じてしまった際にどのようなサポート体制があるのか、事前にチェックしておきましょう。
基本的には24時間365日、専門の技術員が対応してくれるサポートセンターがある会社を選ぶようにしてください。
④価格は?
最後のポイントが「価格」です。価格は導入する台数やメーカーによっても変わってきます。具体的な金額については、各メーカーに問い合わせましょう。/p>
PACS導入のメリット
PACSを導入することで、下記のようなメリットを得ることが可能です。
- 人的ミスの回避
- データ保管が可能
- 患者への説明がスムーズ
ここからは、PACSを導入するメリットを解説していきます。
人的ミスの回避
最初のメリットは「人的ミスの回避」ができるという点です。物理的なフィルムで保管すると、フィルムの取り違えや紛失といった人的ミスが発生するリスクがあります。医療現場において、些細な人的ミスが患者さんの命にかかわるケースも少なくありません。
PACSでは画像をIDに紐づけて、データを保管します。そのため、取り違えや紛失といった人的ミスを回避できるのです。
データ保管が便利
次のメリットは「データ保管が便利」という点が挙げられます。フィルムレス化できるため、フィルムを保管するスペースを削減することが可能です。実際のフィルムのように、膨大な資料の中から目的のフィルムを探す手間や時間もかかりません。
また、データを自由に電子カルテなどの院内機器に送ることもできます。カルテを紙ベースで保管する必要がないため、経年劣化の心配もありません。
患者への説明がスムーズ
最後は「患者への説明がスムーズ」というメリットが挙げられます。PACSなら診断画像をメディアに保管して、患者さんに視覚的に見せることができます。
過去の画像との比較もしやすく、患者さん自身が異常を判断できるので、説明がスムーズに行えるでしょう。
まとめ
近年、医療のIT化は急激に進み、医療用画像管理システムPACSを導入する病院も増えてきています。院内の業務を効率化してくれるだけでなく、人的ミスの予防にもなるため、PACSの導入を検討中の施設も多いでしょう。
PACSはさまざまな企業から販売されており、それぞれの製品に特徴があります。クラウド型かどうか、セキュリティはしっかりしているかなど、当記事で紹介したチェックポイントを確認しながら、製品を選ぶようにしましょう。機能性や操作性も確認しながら、施設にとってベストなPACSを選択しましょう。
- 業界に精通したコンシェルジュが希望に合うサービス・業者を厳選してご案内します
- ご利用は完全無料!