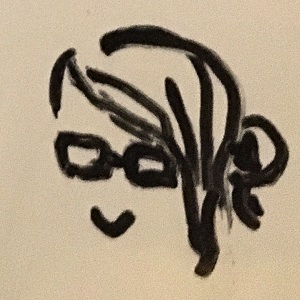クリニックの集患に効くSNS運用とは?成功事例と攻略法を解説

患者様を集めるためには、知名度の向上やブランディングが重要です。クリニックのマーケティングにはSNS(Social Networking Service)が効果的であることをご存じでしょうか。実際にいくつかの病院・クリニックではSNSを活用して、知名度の向上やブランディングにつなげています。
本記事では、各SNSごとの成功事例や攻略方法、クリニックがSNSで発信する際の注意点などについて紹介します。SNSを攻略して患者数を増やし、収益向上を目指しましょう。
SNSの特徴やメリット、デメリットについては病院・クリニックがSNSを活用する効果や各SNSの特徴を紹介!でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
目次
クリニックでSNSを運用するメリット
クリニックでSNSを運用するメリットは以下の通りです。
- 集患効果がある
- リアルタイムで告知ができる
- クリニックのブランディングができる
- 患者さんとコミュニケーションがとれる
- 無料ですぐに利用できる
以下で詳しく解説します。
集患効果がある
SNSでクリニックの特徴や強みをアピールし、患者さんにアプローチすることができます。広く患者さんへ情報を発信することで、患者さんからの問い合わせや来院数の増加につなげることができます。SNSで発信を続けていれば、これまで接点がなかった方にもクリニックを認知してもらえます。SNS上で患者さんからのコメントや「いいね」をもらうことで、クリニックの信頼性向上につなげることも可能です。
リアルタイムで告知ができる
SNSを使うことで、クリニックの情報発信がよりリアルタイムになります。例えば、診療時間の変更や急なお知らせなどをすぐに投稿できます。ホームページを更新する場合はパソコンを立ち上げたり、場合によっては業者に連絡する必要があります。その点SNSであれば、医師やスタッフが簡単に告知を行えます。定期的に発信していれば、それが親近感や信頼感につながり、来院のきっかけになるかもしれません。
クリニックのブランディングができる
SNSの運用はクリニックのブランディングにもつながります。クリニックの情報発信を通じて、クリニックの理念やスタッフの人柄を多くの人に伝えることができます。
患者さんとコミュニケーションがとれる
SNSではコメントや「いいね」でダイレクトにコミュニケーションがとれます。患者さんも個人でSNSアカウントを持っている場合が多いです。ホームページよりも患者さんとの継続的なコミュニケーションがとれるでしょう。
無料ですぐに利用できる
SNSは基本的に無料でいつでも始められるため、広告費用がかかりません。とりあえず試しに始めてみるのもひとつの方法です。
クリニックでSNSを運用するデメリット
クリニックでSNSを運用するデメリットは以下の通りです。
- 運用を続ける手間がかかる
- すぐには集患につながらない
- 炎上のリスクがある
以下で詳しく解説します。
運用を続ける手間がかかる
SNSを運用するには、定期的に投稿を行う必要があります。しかし、クリニックの場合、医師やスタッフが忙しく、SNSの運用に時間を割くことが難しい場合があります。すべての投稿に全力を注ぐのは現実的ではありません。無理のない投稿の頻度やルールを決めて運用すると継続しやすいでしょう。
すぐには集患につながらない
SNSを利用しても、すぐには集患につながらない場合があります。インターネットリテラシーの高い方であっても、SNSを利用してクリニックを探すことは少ないため、基本的に効果が出るまで時間がかかります。特に運用初期はユーザーのリアクションは気にせず、練習のつもりでコツコツ投稿しましょう。運用を続けていくうちに、リアクションがもらえる投稿が分かってきます。
炎上のリスクがある
SNSでの投稿は、誤解を招いたり、不快感を与えたりすることがあります。そのため、炎上するリスクがあることも事実です。炎上すると、クリニックのイメージダウンにつながり、逆効果になることもあります。投稿内容やタイミングについてあらかじめクリニック内のルールを決めておきましょう。
クリニックSNS運用の成功事例と攻略法
SNSといっても、種類は数多くあります。LINEやTwitter(現:X)、Instagramなど、SNSによって特徴が異なるため、同じような使い方をしていては効果的に活用するのは難しいでしょう。よく使われるSNSは以下の通りです。
| 特徴 | 利用率 | |
|---|---|---|
| LINE | 診療予約やお知らせなどダイレクトにメッセージをやり取り | 94% |
| Twitterr(現:X) | 拡散力が強くリアルタイムな情報発信ができる | 45.3% |
| 産婦人科や自由診療のあるクリニックにおすすめ | 50.1% | |
| ホームページのサブとして情報を発信 | 29.9% | |
| TikTok | 美容系・採用活動におすすめ | 28.4% |
出典:令和4年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査|総務省
成功事例として、実際に活用している病院やクリニックを紹介するので、ぜひ参考にしてください。
LINEの成功事例と攻略法
LINEは、今回紹介するSNSのなかで最も利用率が高いSNSです。全年代での利用率が高く、一番利用率が低い60代でも76.2%の方が利用されています。LINEで発信した情報を見てもらうためには、友達登録をしてもらわなければなりません。そのため、ポスターや広告などを利用して、友達登録をしてもらうことが攻略の鍵となるでしょう。
LINEに対応した診療予約システムと連携することで、簡単に患者さんが予約を取れるようになるのもメリットです。LINEで簡単に予約が取れることから集患効果も見込めます。
LINE診療予約についてはLINEを使った予約システムで医療機関の集患を実現|評判やメーカー比較まででも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
LINEの成功事例①医療法人社団 明芳会 高島平中央総合病院
https://takashimadaira-hospital.jp/features/line.html
高島平中央総合病院は、病院内のイベントや外来の担当医表などの基本情報を発信しています。そのほかにも、栄養士が考案したレシピを配信する「TAKACHU KITCHEN」やリハビリ科がストレッチ方法を紹介する「TAKACHU HEALTH」などコンテンツが豊富です。また、通常のLINEのようにトーク画面にキーワードを入力することで、最新情報をチェックできます。
LINEの成功事例②一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院
http://www.kokurakinen.or.jp/byoin/line_at/
小倉記念病院は、最新の医療情報やイベント情報の案内などを発信しています。わかりにくい医療情報をわかりやすく解説している動画もあるので、疑問解消に役立ちます。小倉記念病院ではLINEの友達登録を促すために、医療クイズを投げかけて友達登録をすれば、答えがわかるように工夫しています。テキストはもちろん、画像や動画などの投稿ができ、全年代の利用率が高いため、利用する病院を選びません。
LINEはビジネス用のアカウントがおすすめ
LINEにはプライベートで使用する通常のプランとは他に、ビジネス用のアカウント『LINE公式アカウント』を作ることが可能です。ビジネス用のアカウントでは、友達登録をしている方一斉に情報を送信することができ、個別に情報を発信する手間が省けます。
ビジネス用のアカウントは無料で利用することも可能ですが、送信するメッセージ通数が増えたら、料金が発生する月額課金制です。多くの方に情報を届けたい場合には、有料プランに加入して、発信しましょう。
Twitter(X)の成功事例と攻略法
Twitter(現:X)は、10代〜20代がメインユーザーのSNSです。投稿の際には、140文字以内の字数制限(無料アカウントの場合)や4枚までの画像制限などがあり、わかりやすく投稿内容をまとめる必要があります。
リツイートといわれる投稿を拡散する機能があり、役立つ内容や豆知識、共感を生むようなツイートなど、リツイートしたくなる投稿をすると拡散されやすいので狙っていきましょう。また、フォロワーが少ないうちはフォロワーの多いアカウントのツイートを引用ツイートすることで効果的にインプレッション数(ツイートの閲覧数)を増やしていくことが可能です。関連するツイートをしている有名人や他の病院に積極的に絡んでいきましょう。
リアルタイム性が強いSNSなので、すぐに伝えたい情報を発信する際にも役立つでしょう。コロナ禍であれば、新型コロナワクチンのキャンセル枠について、情報を広めたい時に効果が期待できます。ただし、匿名性が高いSNSであることから炎上しやすい点に注意が必要です。
Twitter(X)の成功事例①亀田総合病院(ちっとばあり公式)

亀田総合病院は、病院内の診療情報や季節ごとの医療的な注意喚起など、数多くの情報を投稿しています。また、現在は新型コロナウイルスのワクチンについての情報や、病院内での感染状況について情報を発信しています。
Twitter(X)の成功事例②西真岡こどもクリニック

https://twitter.com/nishimoka0404
西真岡こどもクリニックは、小児医療に関連した情報を中心に投稿。病院スタッフの仕事を紹介したり、病院内の写真を投稿していたりと、病院の雰囲気が伝わります。
Instagramの成功事例と攻略法
Instagram(インスタ)は、写真や動画がメインとなるSNS。ユーザーの年齢層は10代〜20代で、男性よりも女性の利用率が高い傾向です。
Instagramの投稿では、「映える」魅力的な画像や動画が重要視されており、目を惹きつける投稿が攻略のポイントです。そのため、美味しそうな病院食や生まれた赤ちゃんの写真など、映える画像や動画が投稿できる産婦人科が活用するのに向いています。最近では、1枚目の画像を写真ではなく、ユーザーをひきつけるようなテキストタイトルにするテクニックがトレンドです。
Instagramの成功事例①産婦人科 清水病院

https://www.instagram.com/shimizu_hospital/
清水病院は、彩り鮮やかな病院食や産婦人科に関する情報について投稿しています。写真がメインの投稿と情報発信がメインの投稿を交互に投稿することで、見ていて飽きない工夫がされています。
Instagramの成功事例②岡山済生会総合病院産婦人科病棟【公式Instagram】

https://www.instagram.com/maternity_okayamasaiseikai/
岡山済生会総合病院産婦人科病棟は、生まれた赤ちゃんの写真やご家族との写真を投稿しています。また、画像だけではわかりにくい赤ちゃんの入浴方法やおむつ交換、出産時の呼吸方法など、役立つ情報が動画で投稿されているのもうれしいポイントです。
Facebookの成功事例と攻略法
Facebookはテキストや画像、動画など幅広いフォーマットを活用して、自由度の高い投稿ができるSNSです。実名での登録がほとんどであり、個人が特定できます。
また、ユーザーの年齢層が30代と40代で高いことから、他のSNSと比較して高い年齢層へのアプローチに有効です。Facebookを使用することで、公式ページの雰囲気を作ることができます。成功事例で紹介した病院のように、活動内容や取り組みなど、ホームページのサブとしての利用がおすすめです。
Facebookの成功事例①医療法人財団 荻窪病院

https://ja-jp.facebook.com/ogikubohospital/
荻窪病院は、病院の活動内容や取り組みについて投稿しています。また、病院ホームページに掲載されているリハビリテーション室BLOGへのリンクを掲載して、ホームページへの導線をつなげています。
Facebookの成功事例②医療法人沖縄徳洲会 千葉西総合病院

https://www.facebook.com/pg/chibanishi/posts/
千葉西総合病院は、病院の紹介や活動内容についてFacebookを活用して投稿しています。診療科の新しい情報を投稿もそのひとつです。例えば心臓血管外科が、新しい手術を開始したのであれば、その内容を投稿。他にも無料メール相談などもおこなっており、投稿内にお問い合わせ先のリンクがあるのも特徴的です。
TikTokの成功事例と攻略法
TikTokは、10代〜20代の女性ユーザーがメインのSNSです。15秒〜3分のショートムービー専門のプラットフォームで、目を惹きつけるキャッチーな動画投稿がポイントとなります。10代〜20代の女性にアプローチしやすいため、美容医療の病院やクリニックで効果が期待できるでしょう。ほかにも、病院の働きやすい雰囲気や研修制度を伝えることで、看護師等への採用面でのアプローチができます。
TikTokの成功事例①湘南美容外科クリニック姫路院

https://www.tiktok.com/@sbc_himeji?lang=ja-JP
湘南美容外科クリニック姫路院では、美容医療の施術動画を投稿しています。事前にどのような施術がされるのか確認できるため、患者様の安心感につながるでしょう。
TikTokの成功事例②IMS(イムス)グループ新越谷病院

https://www.tiktok.com/@shinkoshihp2211?lang=ja-JP
IMS(イムス)グループ新越谷病院では、看護師を中心に病院の雰囲気が伝わる投稿がされています。また、病院内でおこなわれている研修や教育制度などの情報を発信しており、職場の雰囲気や働きやすさなどが伝わってきます。
SNS以外にクリニックのホームページは必須!
どのSNSを運用する場合も、クリニックのホームページは用意するのがおすすめです。患者さんがクリニックの場所や診療時間、電話番号などをインターネットで確認できるよう、基本情報を必ずのせておきましょう。各SNSにホームページへのリンクを掲載して紐づけることで、集患を強化できます。
また、ホームページは「医療広告ガイドライン」の対象になります。ホームページ制作を依頼する際は、医療広告ガイドラインを理解したクリニックホームページ制作に実績のある業者を選びましょう。
おすすめのホームページ制作会社については【2023】クリニック・病院におすすめのホームページ制作会社17選でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
医療広告ガイドラインについては【最新版】医療広告ガイドラインをわかりやすく解説!NG・OK表現もでも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
病院がSNS攻略をおこなう場合の注意点
SNSは病院の知名度を高めたり、ブランディングしたりする際に効果的です。しかし、SNSには炎上や情報漏洩などのリスクがあることに注意しなければなりません。ここでは、病院がSNS攻略をおこなう場合の注意点を解説します。
不適切な投稿を避ける
病院がSNSを有効活用するためには、不適切な投稿を避けることです。不適切な投稿が原因となって、批判や誹謗中傷が集まる炎上のリスクが高まります。炎上してしまうと病院にネガティブなイメージが定着して、ブランディングがマイナス方向に働いてしまう可能性があります。そのため、病院の愚痴や医療体制の不満点、仕事に対するネガティブな投稿などは避けましょう。
個人を特定できる投稿を避ける
個人を特定できる投稿は、プライバシー侵害に該当するため注意が必要です。SNSは不特定多数の方が見ており、個人情報が漏洩してしまう可能性があります。個人を特定できる投稿としては、珍しい病名を公表したり、院内の写真を撮影した際に患者様のネームプレートが映っていたりといった投稿です。投稿する前には入念に個人情報が漏洩するリスクがないことを確認したうえで、投稿しましょう。
SNS使用時のガイドラインを作成する
事前にSNS使用に関するガイドラインを作成しておき、投稿する際にはガイドラインに遵守することで不適切な投稿を予防します。投稿時の注意点や記載してはいけない情報を明確にし、炎上や情報漏洩が発生するリスクを軽減させましょう。
投稿者を少人数にしぼる
病院のSNSとはいえ、投稿できる人が多くなれば管理が難しくなります。また、投稿者によって内容が異なってしまうと、情報の一貫性が保たれなくなる可能性があります。投稿者はなるべく少人数に固定して、責任ある立場の方が管理するのがおすすめです。
職員向けにネットリテラシーの研修を行う
病院のSNS運用とは異なりますが、病院の職員が個人のSNSで投稿した内容が病院の炎上や患者様の情報漏洩につながるケースがあります。そのため、職員にSNSを適切に活用するためのルールを周知しておくべきでしょう。職員向けに病院内での勉強会や研修などをおこなって、一人ひとりのネットリテラシーを高めることが安全なSNS利用につながります。
クリニックにおけるSNS運用以外の集患方法
ここでは、インターネットを使ったSNS運用以外の集患方法について解説します。クリニックのホームページやSNSに紐づけて集患を強化しましょう。
【おすすめ】Googleビジネスプロフィール
Googleビジネスプロフィール(旧:Googleマイビジネス)は、無料で利用できるGoogleのビジネス情報登録サービスです。クリニックの情報を登録することで、Google検索やマップ上に自院の情報が表示されます。地域最適化(MEO)や検索エンジン最適化(SEO)に効果が期待できます。無料かつ自分で登録でき、運用にも手間がかからないので最もおすすめです。
MEOについてはクリニックのMEO対策とは?|メリットやツールを徹底解説!でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
SEOについてはクリニックのSEO対策おすすめ企業5選【徹底解説】でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
Googleサーチコンソール
Googleサーチコンソールは、Webサイトの検索トラフィックや掲載順位を測定するためのツールです。自院のホームページが誰にどのくらい見られているかチェックすることで、コンテンツを修正し、Google検索結果でのサイトの注目度を高めることができます。
Googleアナリティクス
Googleアナリティクスは、Webサイトのアクセス解析ツールです。どのような検索でユーザーがホームページにアクセスしているかを確認・分析し、ホームページを改善していけます。
Google広告
Google広告は、Google検索やYouTubeなどのサイト上にて商品・サービスを宣伝できるオンライン広告です。広告掲載の目標(コンバージョン)として、「電話での問い合わせ」や「サイトへの訪問」といった特定の目標も指定できます。クリニック開業時の集患におすすめです。自分で使う費用を決める必要がある点に注意しましょう。
クリニックについてはクリニック開業の流れを徹底解説|時期別のやることリスト・成功に大切なポイントでも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
SNSを攻略し病院の知名度を高めましょう
SNSはうまく活用すれば、病院の宣伝に効果的なツールです。今回紹介したようにSNSを上手に活用している病院やクリニックがあります。今後、患者様に選ばれる病院になるためには、病院のSNSの利用は重要な手段となるでしょう。しかし、SNSには炎上や情報漏洩のように注意しなければならないこともあります。本記事を参考にしてSNSを攻略し、クリニックの集患に役立てましょう。