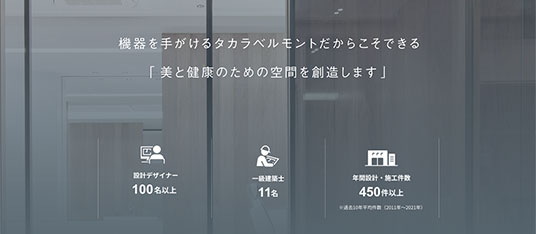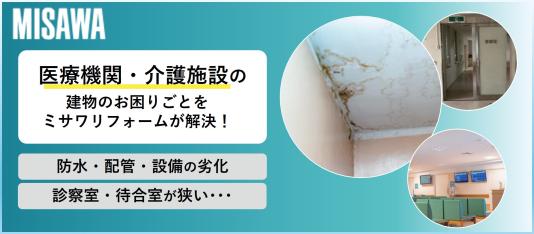軽天(けいてん)とは?内装における軽鉄、LGS工事との違いまで

軽天は、骨組み部分なので人の目に見えることは ありません。また、木造では軽天は不要です。
軽天はさまざまなメリットがあり、非常に優秀な壁・天井材として知られています。
今回の記事では、軽天について詳しく解説していくので、 参考にしてみてください。
軽天(ケイテン)とは?
軽天は、「軽量鉄骨天井下地」の略で、軽量鉄骨を素材とする天井材のことです。
厚さ0.5mm~1mmほどの銅材で作られており、経験を格子状に組み上げて天井や壁の骨組みを作ります。軽天工事は、部屋を区切りたい時に行うものです。
軽天工事では木材が不要で、工事時間が大幅に短縮されるため、低コストで工事ができます。 一般住宅ではまだあまり多くありませんが、店舗や病院などの内装工事では頻繁に行われている工事です。
軽天のメリット
ここでは、軽天のメリットをそれぞれ解説していきます。主に、木造との比較によるメリットを書いていくので、参考にしてください。
耐火性(燃えにくい)
軽天は、主に銅材で作られているため、木材より燃えにくいです。 人が密集する店舗での内装材として優秀で、火災の防止や人命保護の際に役立ちます。
不燃材料でできているため、消防検査にも通りやすいです。また、湿気にも強いので長持ちします。
耐久性の高さ
軽天は、木材よりも耐久性が高いです。木材の場合、乾燥によって割れたり、湿気によって大きさが変化してしまうというデメリットがありますが、軽天にはこういった弱点はありません。
軽天は軽量ですが、十分な強度があるため歪みや曲がりに強いです。湿気の影響も受けないので、虫食いや腐食の心配もありません。
加工のしやすさ
軽天は非常に加工しやすいです。 軽天に使用される銅材は、厚さ1㎜程度と薄く、天井や壁などへの負担も大きくありません。
木材よりも現場での加工がしやすく、状況に合わせてカットすることが可能です。そのため、工期を大幅に短縮できます。
コスパの高さ
木材の場合、重い上に、微調整が必要なので、作業に時間が長くかかってしまいます。軽天は、軽くて加工もしやすいので、原価が安くなり、工期を大幅に短縮可能です。
その結果、全体的なコストダウンにつながります。
軽天のデメリット
軽天のデメリットは、細かい調整がしにくい点にあります。木造との比較によるデメリットを書いていくので、参考にしてください。
細かい調整がしにくい
軽天は、加工しやすいというメリットがありますが、木材のように削って調整することはできません。そのため、現場での柔軟性のある対応には欠けます。
軽天は、メリットとデメリットを考慮して、現場の状況に合わせて使用するようにしましょう。
軽鉄、LGSとの違いは?
ここでは、軽天と、軽鉄・LGSそれぞれの違いを解説していきます。
軽天と軽鉄、LGSの違い
一般的に、天井のことを軽天工事、壁のことを軽鉄工事と言います。また、LGSは、Light Gauge Steel(ライト・ゲージ・スティール)の略で、壁や天井を作る金属でできている下地の事です。
このように、軽天と軽鉄・LGSには、明確な違いはありません。
軽天の構造(仕組み)
ここでは、軽天の構造(仕組み)を解説していきます。壁と天井でそれぞれ使用する部材が異なるので、そのあたりにも注意して参考にしてください。
壁の場合
壁を作る場合は、部材が少なく、格子状に作っていきます。
- ランナー
スタッドを建て込むために、地面と天井に平行に設置する必要があります。釘やビスを使用して設置するのが一般的です。コンクリートに設置する際は、専用の打ち込みガンを使用します。 - スタッド
スタンドには「コの字」タイプと「口型」のタイプがあり、石膏ボートやベニヤ板を貼り付けられるように建て込みます。通常のビスよりも小さく短いビスを使用して、上下のランナーにビス止めしましょう。
スタッドの間隔:300mm~450mm (間隔は、軽天の上に張る材料や石膏ボードの枚数によって異なる) - 振れ止め
スタッドが横に揺れないようにするための補強材として、使用するのが振れ止めです。 天井の高さが高ければ高いほど、振れ止めの本数は増えます。
振れ止めの設置:1200mm - スペーサー
スペーサーはスタッド自体の補強材です。口型タイプであれば潰れませんが、コの字タイプは、衝撃で破損してしまう可能性があります。そのため、補強するためにスペーサーを設置しましょう。
天井の場合
天井の場合は、壁よりも部材が多くなります。
- 吊りボルト
天井から吊るす、全ねじボルトです。ボルトの先端にハンガーを建て込めるようにし、地面に対して垂直になっているかを確認しましょう。ポルトが斜めになっていると、綺麗に仕上がりません。
ボルト同士の間隔:通常900㎜ - ナット
吊りボルトに取り付けて、高さを調整したり、ハンガーを固定したりするために使用します。 - ハンガー
吊りボルトの末端に取り付け、野縁受けを固定できるようにします。 - 野縁受け
ハンガーに固定して、シングル野縁、ダブル野縁を 固定するために使います。 形が「C」の形になっているため、「Cチャン」と言われることもあります。
野縁受け同士の間隔:900㎜ - 野縁受けジョイント
野縁受けの長さが足りない場合に使用します。
野縁受けは4~5mほどありますが、現場によっては一辺の長さが10m以上になることも少なくありません。 - シングルクリップ、ダブルクリップ
野縁受けとシングル野縁、ダブル野縁を固定するために必要です。手で簡単に曲げられるくらい柔らかいタイプと、ボルトで締め付けるタイプの緊結性能が高いクリップの2種類があります。
柔らかいタイプは内装で使用されることが多く、ボルトで締め付けるタイプは外部の天井に使用されることが多いです。 - シングル野縁、ダブル野縁
野縁受けとクリップを使い、固定する長尺の部材です。断面がM字になっているので、Mバーと呼ばれています。
野縁同士の間隔:255mm〜300mm (耐震性や耐風圧によってピッチが変動するため、調整が必要。外部からの影響を受けにくい箇所はピッチが広く、外部からの影響が強そうなところはピッチが短くなる)
天井工事のときは、シングル野縁とダブル野縁のどちらも必要になります。基本的にはシングルを使用し、天井ボード同士のジョイント部分には、ダブル野縁を使用しましょう。 - シングル野縁ジョイント、ダブル野縁ジョイント
長さが足りないときに、野縁同士をジョイントする際に使用します。野縁自体の長さは4〜5mほどですが、廊下や大広間などは一辺の長さが10m以上あるケースが多いです。
軽天を貼った後の作業工程
ここでは、軽天を貼った後の作業工程を解説していきます。工事により違いはありますが、一般的な工程を解説するので、参考にしてください。
- 壁の場合
壁は、天井よりもシンプルです。まず、壁の仕上がりの位置に合わせて、ランナーを取り付けましょう。ランナーの取り付けが終わったら、スタッドを付けていきます。スタッドは壁の土台となる銅材です。ランナーに必要な長さに切断し、はめ込みます。 - 天井の場合
まず、天井のコンクリートの躯体に、ドリルを使って一定間隔で穴を掘ります。その次に、空けた穴にアンカーを打ち込みますが、しっかりと打ち込まなければ脱落の恐れがあるため、慎重に行わなければなりません。
アンカーを打ち込んだら、雌ねじに吊りボルトを 取り付けます。
吊りボルトの先端に、天井材の基礎となる銅材のハンガーを取り付けて、そこに更に長い銅材を取り付け、その下に別の銅材を格子状にビス留めしましょう。
最後は、石膏ボードを格子状になった銅材にビス留めし、クロスなどで仕上げます。
軽天工事の単価はどのくらい?
軽天工事の単価相場は以下の通りです。
- 天井:1,200円~1,500円(平米単価)
- 壁:1,500円~1,700円(平米単価)
- 間仕切り:1,600円~2,100円(平米単価)
軽天工事の単価は、部材価格や場所によって異なるので、あくまで参考として覚えておきましょう。
また、業者により単価の計算方法が異なるので、価格だけで判断するのは危険なので気をつけてください。
内装工事の費用については内装工事の費用はどのくらい?費用相場や物件別の坪単価まででも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
まとめ
軽天と、軽鉄・LGSの明確な違いはありません。木材よりも安価で工事できるので、オフィスや店舗などの、天井・壁の工事におすすめです。
今回の記事の内容をしっかりと理解した上で、軽天工事の依頼をしてみるといいでしょう。