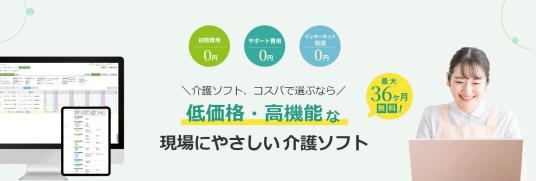インボイスに対応した介護ソフトとは?制度概要、おすすめ製品を紹介

いよいよ2023年10月1日より「インボイス制度」が導入されます。 インボイス制度は免税事業者・課税事業者問わず、全ての事業者に影響がある新しい税制度です。
制度開始までに、事業者登録や請求書・システムの変更などを行わなければならないため、対応が必要な介護事業所は早めに準備を進めておきましょう。
この記事では、インボイス制度の概要や、介護事業所における制度への対応方法、インボイス対応の介護ソフトなどについて解説していきます。
この記事を読むことでインボイス制度の必須知識を得てスムーズな対応が可能となるでしょう。
- 業界に精通したコンシェルジュが希望に合うサービス・業者を厳選してご案内します
- ご利用は完全無料!
そもそもインボイス制度とは
2023年10月1日から開始されるインボイス制度は、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。これは、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を用いた場合にのみ、消費税の仕入額控除を受けることができるという制度です。
インボイス制度は、消費税10%引き上げの改正で、複雑になった消費税を正確に把握する目的で導入され、サービスの売手、買手の両方に影響があります。ここでは、売手側・買手側それぞれの対応について解説していきますので、ご確認ください。
また、この記事では執筆時点での最新情報を記載していますが、インボイス制度については軽減措置や経過措置など、変更点も多いため注意が必要です。国税庁ホームページなどで、随時最新情報をご確認ください。
売手側の対応
まずは売手側の対応についてです。売手側はおおまかに分けて4つ対応すべきことがあります。
- 発行事業者への登録
- 必要な記載項目の追加
- インボイスの交付
- インボイスの保存
発行事業者への登録
インボイスの発行事業者となるためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、発行事業者として登録する必要があります。
必要な記載項目の追加
発行する請求書・領収書・納品書・レシートをインボイスの要件を満たしたものにするために、記載項目を追加しなければなりません。必要な記載項目は以下の通りです。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
インボイスの交付
買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
インボイスの保存
インボイス制度施行後は、交付したインボイスの写しを7年間保存する必要があります。
買手側の対応
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、売手である登録事業者から発行されたインボイスを7年間保存する必要があります。
介護事業所のインボイス制度対応方法
介護事業者は一部(自費サービスや配食サービスなど)を除き、提供サービスが消費税対象外のため、免税事業者である場合が多いです。
しかし、取引先に課税事業者がいる場合などはインボイス制度への対応が必要となるでしょう。ここでは、介護事業所のインボイス制度の対応方法について、免税事業者と課税事業者に分けて解説していきます。
現在免税事業者である介護事業所のインボイス制度対応方法
現在、免税事業者である介護事業所は、取引先に課税事業者がいるかどうかが、対応方法を決める重要なポイントになります。サービス提供先が利用者個人のみの場合はインボイス発行事業者へ登録しなくても問題はありません。
しかし、取引先に課税事業者がいる場合は発行事業者への登録を検討した方が良いでしょう。なぜなら、介護事業所がインボイス制度に登録していないと、買手である取引先が仕入税額控除を適用できず、税負担が大きくなってしまうからです。
この場合、取引先から値引き交渉をされたり、仕入先を変更されたりして、損失が出てしまう可能性があるでしょう。インボイス発行事業者に登録し課税事業所になると、上記のような損失は避けられますが、納税の義務が発生してしまいます。インボイス発行業者に登録するかは、予測される損失と納税額を確認し、慎重に検討しましょう。
現在課税事業者である介護事業所のインボイス制度対応方法
課税事業者の場合も免税事業者と同様に、取引先に課税事業者がいるかどうかがポイントになります。サービス提供先が利用者個人のみの場合は、インボイス発行事業者に登録しなくても問題はありません。
しかし、課税事業者が取引先にいる場合は、介護事業所がインボイス発行事業者に登録していないと、取引先側の税負担が大きくなってしまいます。この場合はインボイス発行事業者に登録した方が良いでしょう。
インボイスに対応した介護ソフトとは?
介護ソフトの中には、インボイス(適格請求書)の発行に対応しているものもあります。インボイス対応介護ソフトを利用すると、必要項目が記載された請求書などが発行でき、制度へのスムーズな対応が可能です。介護ソフト導入の際にはインボイス対応の可否も含めて検討してみるとよいでしょう。
インボイス制度に対応した介護ソフト
ここでは、インボイス制度に対応した介護ソフトをご紹介します。
まもる君クラウド

まもる君クラウドはクラウド型の介護ソフトです。記録から請求まで一気通貫に行うことが可能です。パソコンだけではなく、タブレットにも対応しているので、どこからでも記録の入力を行うことができます。
最新の機能にも対応しており、ケアプランデータ連携やLIFEにも完全対応しています。常に最新の応対でサービス利用することができます。これだけの機能が充実しているにも関わらず初期費用は0円で月額費用も業界水準ではかなり安い部類になっています。
まもる君クラウドの比較ポイント
- 初期費用0円で月額費用も低価格
- 科学的介護情報システム(LIFE)対応
- ケアプランデータ連携にも対応
まもる君の評判・料金などについてはまもる君クラウドの評判・口コミは?料金やメリット・デメリットも解説でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
ナーシングネットプラスワン

ナーシングネットプラスワンは全国6,000以上の事業所に導入されている介護ソフトで長年利用者からは使いやすいという評価を受けている製品です。特に導入費・サポート費・更新費が掛からずプランによりますが、月額8,000円から利用を開始することが可能です。
インボイス以外にもケアプランデータ連携やLIFEにも対応しており、低価格で多機能なソフトとなっています。
ナーシングネットプラスワンの比較ポイント
- 全国6,000事業所以上での導入実績があり安心
- 初期費用・更新費用・サポート費用が無料
- アプランデータ連携や科学的介護情報システム(LIFE)にも対応
カナミック
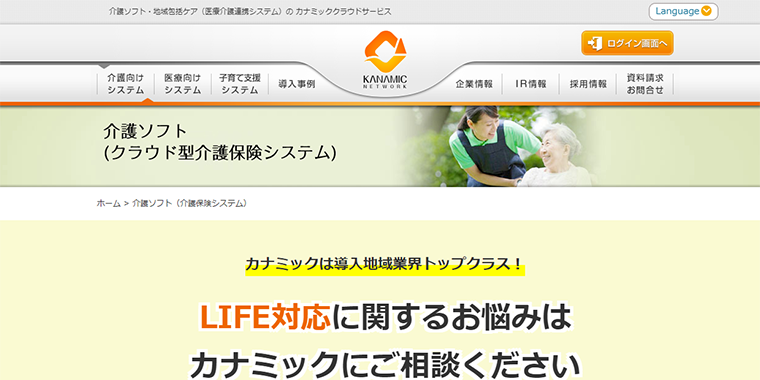
カナミックのクラウド型介護事業ソフトは、約38,800事業所の導入実績がある介護ソフトです。
特徴としては、インターネット環境があれば端末や台数を気にせず、いつでも・どこでも情報の共有ができることが挙げられます。
医療・看護・介護・自治体といった多職種他法人間の垣根を越えた情報共有は、地域包括ケアに必須のため、このクラウドサービスは大いに役立つでしょう。
また、科学的介護情報システム(LIFE)対応や、経営状況の分析・把握など、多彩な機能が搭載されている点も魅力です。
カナミックの比較ポイント
- 約38,800事業所の導入実績
- 科学的介護情報システム(LIFE)対応
- クラウドサービスで情報共有を容易に
ほのぼのNEXT

ほのぼのNEXTは、72,000を超える導入実績がある、業界トップシェアの介護業務支援ソフトです。
特徴としては、介護保険、障がい福祉、財務や給与など、機能のラインナップが充実していることが挙げられます。
また、記録のタブレット入力や音声入力、デジタルインカム、AIケアプランなど、最新技術で介護現場のサポートしてくれる点も魅力です。
介護報酬改定に関わるバージョンアップ無料など、万全のサポート体制も選ばれる理由でしょう。
ほのぼのNEXTの比較ポイント
- 72,000を超える事業所で導入実績あり
- 介護保険、障害福祉、財務、給与など充実のラインナップ
- 最新技術で介護現場をサポート
まとめ
この記事では、インボイス制度の概要や、介護事業所におけるインボイス制度への対応方法、インボイス対応介護ソフトなどについて解説しました。
介護事業者は多くの提供サービスが消費税対象外のため、免税事業者である場合が多いです。まずはインボイス発行事業者に登録する必要があるか確認をしてみましょう。
また、発行事業者に登録する場合には、制度へのスムーズな対応が可能となるため、インボイス対応介護ソフトの利用がおすすめです。最新情報を確認しながら、制度開始に間に合うよう早めに準備をすすめていきましょう。
介護ソフトについては【2023年版】おすすめ介護ソフト29製品を徹底比較|選び方まででも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
- 業界に精通したコンシェルジュが希望に合うサービス・業者を厳選してご案内します
- ご利用は完全無料!