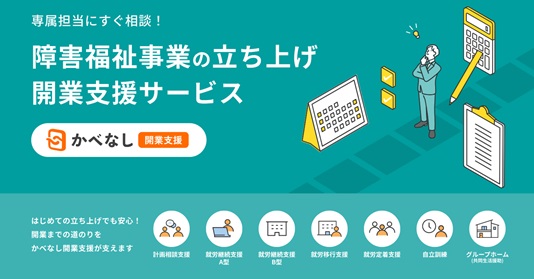整形外科の開業成功ポイント|開業資金や想定年収、経営戦略を解説

「整形外科クリニックを開業するにはいくらぐらい必要なの?」
「開業を成功させるためには、どのような点に気を付けたらいいの?」
このような疑問をお持ちの先生もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では整形外科クリニックの開業に必要な開業資金や、開業を成功させるためのポイントなどを解説しています。開業を検討されている先生はぜひ参考にしてみてください。
- 「勤務医として働きながら膨大な準備や情報収集、情報の精査をするのは大変」
- 「そもそも何から手を付ければいいのかわからない」
- 「大きな決断となる医院開業。信頼できる企業にコンサルティングを依頼したい」
現在、上記のようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひとも私たち「2ndLabo」にご相談ください。開業に必要な情報をまとめた業界最大級の独自データベースとコンシェルジュの知見で開業準備、そして開業成功に向け伴走いたします。
相談は無料です。コンサルティング会社を複数比較したい、開業準備や計画に対するアドバイスが欲しいなど、何でもお気軽にお問い合わせください。
特典資料「時期別!クリニック開業までのやることリスト全まとめ」もプレゼント中です。
目次
整形外科クリニックを取り巻く経営環境は?
整形外科を標榜するクリニックは全国に12,439施設(クリニック総数の12.1%)あります。この施設数は内科、小児科、消化器内科、循環器内科に次いで多い施設数になります。下記の表は整形外科を標榜するクリニック数の推移を示しています。足元では、整形外科を標ぼうするクリニック数はやや減少していることが分かります。一方で、整形外科の競合にあたる整骨院・接骨院、通所介護事業所などの施設数は年々増加しています。クリニックの業績を伸ばすためにはこれら事業所への対応が必須です。
| 2011年 | 2014年 | 2017年 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 12,252施設 | 12,792施設 | 12,675施設 | 12,439施設 |
出典:厚生労働省|医療施設調査
整形外科クリニックの開業資金はどれくらい必要?
整形外科クリニックの開業資金の相場は6,000万円〜8,000万円程度です。戸建開業の場合には1億円以上の資金が必要になります。整形外科はリハビリを実施するためのスペースが必要なため、他の診療科と比較して、土地・建物面積が広くなる傾向があります。一般的に整形外科で必要な坪面積は60~70坪程度だと言われています。
自己資金はどの程度必要?
一般的に開業に要する総費用の1割~2割程度は自己資金として準備することが望ましいです。1,000万円程度は先生ご自身で準備出来ると良いでしょう。
開業資金の資金調達方法とポイント
クリニック開業の開業資金の調達方法は、下記のように先生ご自身で準備する以外に、公的機関や民間金融機関から調達する方法もあります。それぞれ、融資を受けるための条件や融資の上限額が異なるため、詳しくは開業コンサルや税理士に相談してみると良いでしょう。
- 日本政策金融公庫から借りる
- 銀行・信金から借りる
- 福祉医療機構から借りる
- リース会社から借りる
- 補助金・助成金を活用する
- 自己資金を用いる
開業資金の資金調達方法については【診療科目別】クリニック開業資金はどれくらい?自己資金の必要額までで詳しく解説していますので、ぜひこちらもご確認ください。
整形外科クリニックを開業した先生の平均年齢はどれくらい?
整形外科に限ったデータではありませんが、日本医師会が開業医を対象に行ったアンケートによると、医師がクリニックを開業する平均年齢は41.3歳という結果が出ています。医師としてのキャリアや開業までの準備期間、開業医としてこれから働く年数を考えると、30代後半から40代前半が、開業するのに最も適した時期だと言えるのではないでしょうか。
出典:社団法人 日本医師会|開業動機と開業医(開設者)の実情に関するアンケート調査
医師が開業する平均年齢については医師が開業する平均年齢や適齢期はどれくらい?具体例も交えて解説でも解説していますので、あわせてご確認ください。
整形外科クリニックで働く医師の平均年齢は?
続いて、整形外科クリニックで従事する医師の平均年齢は60.9歳です。クリニック全体での医師の平均年齢が60.2歳のため、ほぼ平均通りだと言えるでしょう。
出典:令和2(2020)年 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況
整形外科クリニックを開業した場合の年収は?
整形外科クリニックでの平均年収は2,988万円です(個人クリニックの場合)。全診療科の平均年収が2,505万円のため、他科と比較して高い年収が見込めると言えるでしょう。
| Ⅰ.医業・介護収益 | 9,666万円 |
|---|---|
| Ⅱ.医業・介護費用 | 6,678万円 |
| Ⅲ.所得(Ⅰ-Ⅱ) | 2,988万円 |
開業医の年収については開業医の年収・働き方とは?勤務医時代とどう違う?でも詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
整形外科クリニックの患者数や診療単価はどれくらい?
それでは、いざ整形外科クリニックを開業をした際に、どの程度の外来患者数、診療単価になるのでしょうか。患者数や診療単価を把握することで、収支のシュミレーションを立てることができます。順々に見ていきましょう。
整形外科クリニックでの外来患者数は?
整形外科クリニックで目標とされる外来患者数は1日に100人程度だとされています。他の診療科と比較して診療単価が低いため、その分多くの患者様を診察する必要があります。なお、リハビリ施設を併設しているクリニックの場合、1日に200人以上の患者数が必要になります。
整形外科クリニックの平均診療単価は?
整形外科の平均診療単価は3,000円前後です(院外処方の場合)。一般内科の平均診療単価が5,800円程度だと言われていますので、他の診療科と比較すると診療単価は低く設定されています。後述しますが、運動器リハビリテーション料は比較的高い診療報酬が設定されています。運動器リハビリテーション料を算定するためには、いかに理学療法士や作業療法士を採用できるかが大事になってきます。
整形外科クリニックの開業を成功させるためのポイント・注意点
ここまでに述べてきたように、整形外科クリニックは施設数も多く、整骨院や接骨院、通所リハビリ施設など競合となる事業所が多くあります。また、診療単価も他の診療科と比較して低く設定されています。これらのことからも、他のクリニックや事業所との差別化を図ると同時に、売上を確保していくための工夫が必要です。ここでは整形外科クリニックの開業を成功させるためのポイントと注意点について解説していきます。
PT/OTの採用に力をいれる
整形外科クリニックでリハビリを行って行く場合には、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)の存在は必要不可欠です。PT/OTを安定して雇用できるかどうかが、クリニックの経営に大きく左右すると言っても過言ではありません。クリニックに勤務するPT/OTの人数に応じて、運動器リハビリテーション料で算定できる点数が変わってくるからです。
運動器リハビリテーション料
運動器リハビリテーション料とは、運動器疾患をかかえる患者様に対してリハビリを行った際に算定するものです。(Ⅰ)~(Ⅲ)の3つの区分があり、それぞれ算定できる点数と、取得するための要件が異なります。今回は細かい要件は割愛しますが、それぞれの区分で算定できる点数と人員基準を紹介します。
| 区分名 | 保険点数 | 人員基準 |
|---|---|---|
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 185点/単位 | ・常勤医師が1名以上勤務 ・PTまたはOTがあわせて4名以上勤務 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅱ) | 170点/単位 | ・常勤医師が1名以上勤務 ・PTまたはOTがあわせて2名以上勤務 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅲ) | 85点/単位 | ・常勤医師が1名以上勤務 ・PTまたはOTがあわせて1名以上勤務 |
こちらの表からも、運動器リハビリテーション料(Ⅲ)と(Ⅱ)で保険点数が大きく変わってくることがわかるかと思います。なお、PT / OTが在籍していないクリニックで物理療法(器具による療法)を行った際には、消炎鎮痛等処置を算定します。この場合に算定できる保険点数が35点のため、運動器リハビリテーション料の施設基準を届け出ているかどうかで、売上に大きな差が生じます。
一方、物理療法のみで整形外科クリニックを開業すると人件費が抑えられるメリットがあります。また、診療単価は低くなりますが、患者数を多くこなすことができるのもメリットです。コンセプトにあわせて選択しましょう。
介護保険による通所リハビリテーションを行う
整形外科クリニックを開業する際に、通所リハビリテーションを行うことは、様々なメリットがあります。通所リハビリテーションとは、要介護認定を受けた方が日帰りで通い、医師や理学療法士(PT)などの専門職から身体機能の維持・回復を目指すリハビリを受けることです。通所リハビリテーションは介護保険の範囲です。現在、健康保険法の保険医療機関に指定されたクリニックは、通所リハビリテーションを行う事業者として指定されたものとみなされています。(みなし通所リハ)
整形外科クリニックが通所リハビリテーションを行うことで、以下のようなメリットがあります。
- 医療保険の期限が切れた後も、介護保険でリハビリを提供できる
- 利用者を一定数以上増やすことで収入を増やせる
運動器疾患の患者さんに対して、医療保険で算定できる運動器リハビリテーションの期限が切れた後も、介護保険で継続的なリハビリを提供できます。将来的には外来の患者さんが通所リハビリテーションに移行できるとよいでしょう。
通所リハビリテーションは、医療保険と違って単価が決まっているため、利用者数を増やすことで収入を増やすことができます。一般的には、月の登録者数100名以上、収入は250万円以上が目標とされます。
通所リハビリテーションを行うためには、医師や理学療法士(PT)などの人員や設備の基準を満たす必要があります。また、近隣施設のケアマネージャーへの周知や連携が非常に重要です。通所リハビリテーションは、整形外科クリニックにとって有効な開業戦略ですが、事業計画や運営方法については十分に検討しましょう。
自由診療を行う
整形外科クリニックでは、リハビリテーションの他、自由診療で収益を上げる方法もあります。整形外科で実施できる自由診療の例としては、にんにく注射やプラセンタ注射、グルタチオン注射、PRP治療、ブロック注射などがあげられます。PRP治療とは、血小板の成長因子を使って組織の修復を促す治療法です。ブロック注射は痛みがある場所の神経の近くに局所麻酔を打つことで痛みを軽減する方法です。
自由診療を行う際、患者さんは医療保険を使えず自費扱いになるため、費用や効果についての明確な説明が重要です。
高齢者の来院が多い場合「骨密度測定装置」の導入を検討する
高齢者の多い地域で開業する場合、「骨密度測定装置」の導入はぜひ検討してみてください。2020年(令和2年)の診療報酬改定にて、DEXA法で腰椎撮影を行った場合の保険点数が360点に引き上げられました。十分に採算を取ることが可能な保険点数です。骨密度測定装置を導入することで他院との差別化にもつながります。
患者様が移動しやすい内装・設計にする
整形外科の内装は、比較的広めな内装にすると良いでしょう。通路や入り口が狭いと、車椅子や松葉杖を使った患者様が動きづらく、ケガにつながってしまう可能性もあります。床が滑りにくい素材になっているか、バリアフリーに対応しているか、手すりやスロープが設置されているか等、足腰の悪い方でも移動しやすいように工夫が必要です。
クリニックの内装についてはクリニックの内装の基本を解説|設計時の注意点やおすすめ業者まででも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
まとめ
今回の記事では整形外科クリニックの開業について解説してきました。整形外科クリニックは施設数も多く、その上、競合にあたる整骨院や接骨院、通所介護事業の数も多い診療科です。診療単価も他の診療科と比較して低く設定されており、売上を確保していくためには、診療報酬体系を良く理解して、戦略を練る必要があります。整形外科クリニックの開業を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
クリニック開業関連コンテンツ一覧
- 「勤務医として働きながら膨大な準備や情報収集、情報の精査をするのは大変」
- 「そもそも何から手を付ければいいのかわからない」
- 「大きな決断となる医院開業。信頼できる企業にコンサルティングを依頼したい」
現在、上記のようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひとも私たち「2ndLabo」にご相談ください。開業に必要な情報をまとめた業界最大級の独自データベースとコンシェルジュの知見で開業準備、そして開業成功に向け伴走いたします。
相談は無料です。コンサルティング会社を複数比較したい、開業準備や計画に対するアドバイスが欲しいなど、何でもお気軽にお問い合わせください。
特典資料「時期別!クリニック開業までのやることリスト全まとめ」もプレゼント中です。